特殊要素モデル
| 経済学 |
|---|
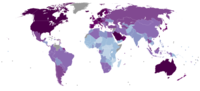 地域別の経済 |
| 理論 |
| ミクロ経済学 マクロ経済学 数理経済学 |
| 実証 |
| 計量経済学 実験経済学 経済史 |
| 応用 |
| 公共 医療 環境 天然資源 農業 開発 国際 都市 空間 地域 地理 労働 教育 人口 人事 産業 法 文化 金融 行動 |
| 一覧 |
| 経済学者 学術雑誌 重要書籍 カテゴリ 索引 概要 |
| 経済 |
|
|
|
特殊要素モデル(とくしゅようそもでる、英:The specific-factors model)は、リカード・モデルに複数の生産要素を導入して拡張した貿易モデル。産業間で移動可能な労働の他に、産業特殊的な(産業間を移動できない)生産要素を導入したモデルである[1]。デヴィッド・リカードとジェイコブ・ヴァイナーに因んでリカード=ヴァイナー・モデル(英:The Ricardo–Viner model)とも呼ばれる[2]。
歴史
ジェイコブ・ヴァイナーの1932年の論文が特殊要素モデルのアイディアを提示した最初の論文とされる[2]。その後、ロナルド・ジョーンズやポール・サミュエルソンらの貢献によって厳密な理論として整理された[3][4][5]。
概要
典型的には、モデル内に国が2つ存在し、それぞれの国に2つの産業(つまり2つの財)と3つの生産要素が存在する。財は国際的に取引されるが、生産要素は国家間を移動するこができない。労働は国内の産業間を移動でき、2つの財いずれかを生産するのに用いることができる。さらに、産業間を移動できない産業特殊的な生産要素も存在する[注 1]。これにより、他の生産要素の投入量を固定して労働の投入量を増加させると、労働の限界生産性が逓減することになる[7]。これによって、産業間で名目賃金が均等化するように産業間の労働者の配分が決定することになる。
モデルの予測
このモデルは、貿易によって輸出促進産業に特殊的な生産要素を持つ経済主体の所得(その産業に特殊的な生産要素の限界生産物価値)が増加し、輸入競争産業に特殊的な生産要素を持つ経済主体の所得が減少することを予測する[8]。労働者の実質所得については、労働者の効用関数を特定しない限り明確な結論は得ることができない[注 2]。このような実質賃金に対する不明瞭な影響は「新古典派的曖昧さ(英: The neoclassical ambiguity)」と呼ばれる[5]。
リカード・モデルでは貿易によってすべての経済主体が利益を得るという結果が得られたが、特殊要素モデルでは貿易によって所得格差が拡大することが予測される。これによって国内に貿易に反対する人と賛成する人が存在する理由を説明できる。
特殊要素モデルに動学的な側面を加え、産業特殊的な生産要素が産業間で移動できるように仮定を緩めることもできる。このとき、特殊要素モデルはヘクシャー=オリーン・モデルとなる[9]。この意味で、特殊要素モデルはヘクシャー=オリーン・モデルの短期版と言える[注 3]。
拡張・応用
中間財を産業特殊的生産要素として導入して、特殊要素モデルの理論的予測がどのように変化するかを検証している論文がある[5]。
脚注
注釈
- ^ このような産業間を移動できない生産要素が入ったモデルをパティ=クレイ・モデル(The Putty-Clay model)と呼ぶ[6]。Puttyはパテ、Clayは煉瓦の意味であり、固まって動かないという意味である[6]。
- ^ 名目賃金については明瞭な結果が得られる。しかし、財の価格も変化するため、それを考慮した実質賃金を計算するには、消費者がそれぞれの財をどれくらい消費するかを知る必要がある。
- ^ 製造業セクターと農業セクターの2産業のヘクシャー=オリーン・モデルを考える。そこでは、資本と労働という2つの生産要素があり、ともに産業間を移動できる。短期分析をする際は、製造業に留まって動かない資本を製造業資本と呼び変え、農業セクターに留まって動かない資本を土地と呼び変える。これは特殊要素モデルとして解釈できる。
出典
- ^ Leamer, Edward; Levinsohn, James (November 1994) (英語). International Trade Theory: The Evidence. Cambridge, MA. doi:10.3386/w4940. http://www.nber.org/papers/w4940.pdf.
- ^ a b Viner, Jacob (1932) "Cost Curves and Supply Curves" Zeitschrift für Nationalökonomie, 23-46.
- ^ Jones, Ronald W. (1971). "A Three Factor Model in Theory, Trade and History." In: Trade , Balance of Payments and Growth, edited by J. Bhagwati et al., Amsterd.
- ^ Samuelson, Paul A. (1971) "Ohlin Was Right" The Swedish Journal of Economics, 73(4): 365-384.
- ^ a b c Ishikawa, Jota (2000) "The Ricardo-Viner trade model with an intermediate good" Hitotsubashi Journal of Economics, 41(1): 65-75.
- ^ a b 木村福成(2000)『国際経済学入門』日本評論社、87ページ。
- ^ Krugman, Paul R.; Obstfeld, Maurice; Melitz, Marc J. (2015) International Economics Theory and Policy. Pearson Education Limited. pp.83-97. ISBN 1292019557
- ^ Krugman, Paul R.; Obstfeld, Maurice (1997). International Economics: Theory and Policy (4th ed.). Reading, Mass.: Addison-Wesley. pp. 40–60. ISBN 978-0673524973. OCLC 34886635. https://archive.org/details/internationalec200krug/page/40
- ^ Neary, J. Peter (1978). “Short-Run Capital Specificity and the Pure Theory of International Trade”. The Economic Journal 88 (351): 488–510. doi:10.2307/2232049. ISSN 0013-0133. JSTOR 2232049.
| |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本概念 |
| ||||||||||||
| 理論・議論 | |||||||||||||
| モデル |
| ||||||||||||
| 分析ツール |
| ||||||||||||
| 結果 |
| ||||||||||||
| 貿易政策 |
| ||||||||||||
| トピック |
| ||||||||||||
| 近接分野 | |||||||||||||
| Category:国際経済学 Category:貿易 Category:国際経済学者 | |||||||||||||









